『桶狭間の合戦』をテーマに徒歩で信長の足跡をたどる旅🐾🐾
~ 後編 です

これまでのお話⤵
須磨扮する信長(のぶにゃが)とともに 桶狭間古戦場に向けて清洲城を出発したすまりんたち...

KFCで腹ごしらえを済ませ 12時25分の再出発!

お昼のためにちょっと大回りしてしましたが...
ここから鳴海街道を南下して丹下砦に向かいます🐾🐾

距離はたったの2.3kmですが 昼下がりの炎天下はかなりこたえました^^;

鳴海街道は台地の上を進む見晴らしのよい道です

ここで街道から道をそれて…

鳴海神社の森の裏を抜け 舌状台地の端にある丹下砦へ🐾🐾

住宅街の民家の庭先に丹下砦跡の看板がありました↓


丹下砦は 当時今川方の手にあった鳴海城を包囲するために築かれたもので 砦の大部分は現在 光明禅寺というお寺になっています


当時は高台から 鳴海城が見えたはずですね

敵方の城ですが 鳴海城にも行ってみます(^_-)-☆
小さな谷を挟み 直線距離わずか500mの至近に鳴海城跡はあります

城跡は公園になっていました

鳴海城には今川家の重臣 岡部元信が入って守備についていました
信長は周囲に丹下・善照寺・中島の砦を築いて これに対抗していました
向こうに見える森のあたりが 丹下砦のある場所でしょうか

信長攻路のプレートがありました⤵
鳴海街道をはさんだ天神社に鳴海城跡の記念碑がたてられていました



元信は 桶狭間で今川義元が討ち取られた後も 織田方の軍勢をことごとく撃退して鳴海城を守り抜きました

最終的に 主君義元の首級と引き換えに開城して 棺を先頭にゆうゆうと駿府へ引き払ったのだそうです
続いて善照寺砦へ向かいます🐾🐾
『信長公記』には「先ず丹下砦へ出られ それから善照寺の佐久間信盛が在陣する砦へ出られて 兵を集めて軍勢を揃えられ 戦況をご覧になる…」と記されています

上の地図で見ると 鳴海城と善照寺砦は丘の両端にあり 本来ならば一つの城の本丸と出丸ぐらいの近い位置で対峙しています
もともと善照寺という寺があって 鳴海城の出丸の役割を果たしていたところを 織田方が奪って要塞化したのでしょうか?
善照寺は名前と場所を変えて 先ほどの天神社の隣に今も存在しています
今は圓龍寺(えんりゅうじ)と言うようです

こちらが善照寺砦跡

「砦公園」になっています


物見櫓?笑⤵が建っていましたが 松の木であまり視界はよくないです

桶狭間はこちらの方角です

時刻は13:30
史実の時刻より遅れ気味です
… やっぱり馬にはかなわない^^;
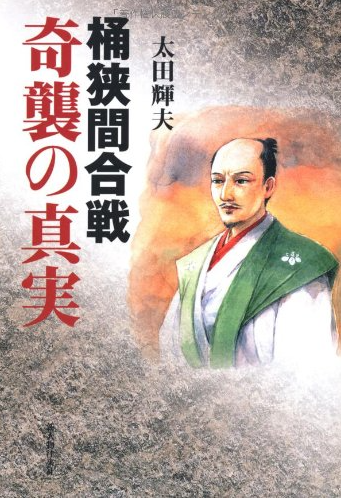
太田輝夫先生の説によれば 善照寺砦から信長の家臣 佐々隼人正ら300人の部隊が先発して 今川軍の攻撃に向かったのだそうです
『中古日本治乱記』という豊臣秀吉の祐筆(書記官)によって書かれた文書によれば「信長の大先手は佐々隼人正正道・千秋四郎大夫良文 信長の瓜紋の旗差揚て向ふ」とあります
つまり 佐々らは 信長本人になりすましていました!
今川軍の先頭は 今川家重臣の松井宗信率いる900人の部隊です

佐々らは桶狭間近くの「釜ヶ谷」という場所に潜み 信長の旗印✨をかかげ 昼頃に行軍してきた松井隊と桶狭間村(現在の桶狭間公園付近)で戦闘に及びました
こちらが「釜ヶ谷」です⤵


2万5千の今川軍の隊列は2㎞にも達していました
先頭から約1km後方にいた今川義元は 伝令から敵襲来の報せを聞き 即座に桶狭間村へ主力戦闘部隊を送り出すとともに 進軍をストップして臨時の本陣を構えました
本陣の場所は田楽狭間とよばれる場所(現在の桶狭間古戦場伝説地)です
佐々らは当初優勢に戦いましたが やがて続々と送り込まれてくる兵に囲まれて討たれてしまいました
今川軍は信長の旗を掲げた武将を信長だと思い込み 戦勝の祝宴が開かれることになりました
徳川氏の家伝『松平記』では「今朝の御合戦御勝にてめでたしと鳴海桶狭間にて昼弁当まいり候…」とあり まるで信長の大将首をとったような喜びに浮かれる様が記されています
一方の信長は戦況をみながら 二千の兵で中島砦に向かいました

中島砦は川の合流点にありました

石碑は私有地にあり柵の外から撮影しましたが 草が茂って隠れています^^;


ここからさらに今川軍に迫ろうとする信長を家臣たちが無謀だと引き留めようとしましたが 信長は「敵は夜通し歩いて戦い 疲れた武者である 一方こちらは新手で疲れもない…」と諭したのだそうです
すまりんたちは日の出前から歩き通しで 十分に疲れていますが(笑)
中島砦を後にした信長は 扇川の土手を東に向かい 山際へと進みました

昼下がりの炎天下... くらくらしました^^;
当時は この辺りで急に大雨が降りだしたそうです!

雨の中 炎天下 敵に気付かれないよう 丘を越えていきます🐴🐾🐾

水分補給を忘れずに(^_-)-☆

歩道橋がつらかったです...

また喉が渇いてきました^^;
自販機を探しながら丘の続く尾根道を進んでいきました🐾🐾

たしかにここは 尾根の裏側に身を隠しながら進みつつ 眼下に敵の様子が窺える奇襲に適したルートだと思いました💡
ファミマです(*^^*)

ドリンクよりも ガリガリ君♡
殿もどうぞ (*^^*)


奇しくもこのファミリーマート太子二丁目店のあたりが 信長が奇襲のチャンスを窺って待機していた「北谷」と推定される場所になります☝
尾張徳川家に伝わった『桶狭間合戦申伝写』には「閑道扇川を上りて 会下山 北谷あたりに御着陣」と記されているそうで 会下山は下図の太子ヶ根にあたるようです

※「桶狭間合戦 奇襲の真実」太田輝夫より
この地方には「根」のつく地名が多くあり 峯・嶺に通じるもので山の山頂を示す言葉だそうです
上図の「太子ヶ根」付近は宅地開発で削り取られ 丘はなくなっています
一般的には 現在「大将ヶ根」と呼ばれている高台が 古くは「太子ヶ根」とよばれ 信長が当地で兵を結集して旗揚げをしたことから「大将ヶ根」と名付けられたとする説が流布しています
大将ヶ根には知多半島を潤す愛知用水が通っていて公園になっています

丘陵の南端が 大将ヶ根

義元本陣(田楽狭間)をすぐ目の前に見下ろす高台ですが 向こうからもバレバレなのでここに軍を集結させて奇襲するのは難しそうです!

丘を下り…
もう一度水分補給(これでも足りないくらいでした^^;)

義元本陣はすぐそこです(^_-)-☆
藤田医科大学の昔のキャンパスだった茶色い時計塔の裏になります


こちらが田楽狭間の義元本陣と伝わる場所です

まもなく15時15分...
出発してからちょうど9時間で到着しました🚩

「すわ かかれ!かかれ!」
諸将をあつめて戦勝の宴会をひらいていた義元本陣に織田軍が襲い掛かりました
太田輝夫先生の説によれば 今は高徳院のある西側の山の上からと 南側から迂回した隊の二手で挟み撃ちにしたようです



到着時はボランティアのガイドさんがおられ パネルが置かれていました

『今川義元戦死所』の のぼり

こちらがお墓だそうです


※義元が実際に亡くなったのはこの場所ではなく 300人程の護衛とともに国道の方に逃れたそうです
追いすがる織田軍と五度ほど戦って味方が50人に減り ついに400mばかり東に行った場所で深田に足をとられたところを毛利新助に討ち取られたと伝わっています
公園の向かい... 西側の山には高徳院が建っています

明治になってからできたもので 当時からあったお寺ではありません

境内には今川義元公本陣跡の石碑がありました


境内裏手の墓地横には松井宗信の墓がありました
今川軍の先頭で佐々隊を打ち破った宗信ですが 義元とともに討たれてしまいました

疲れ切った身体にむち打って 残りの史跡をまわりました🐾🐾

すまきは腰が曲がっているのではなく地図を見ているのです(^_-)-☆
すまりんは地図を見るのが苦手なので 道案内は基本すまきに任せきり(笑)
信長の影武者として死を決して敵陣に突撃した佐々隼人正たちのなきがらは 戦場近くに葬られたと伝わります

塚のひとつが 宅地のまんなかに残されていました👀



塚の真横が一般家庭のお庭だったので ちょっとびっくり!


桶狭間合戦の戦功第一は 義元の首を取った毛利新助ではなく 義元本陣の情報を知らせた簗田出羽守で三千貫文をもらったとされています
この話は信長が情報戦を重要視していた例としてよく知られていますが 実は佐々隼人正の弟の佐々成政は八千貫文の褒美を賜っていたとの話があり 信長がおとりとして死んだ隼人正の功績を最も評価していたことがうかがえます✨
七ツ塚から300mほど南にある「桶狭間古戦場公園」


このあたりで松井隊と佐々隊の戦闘がありました
古くから多くの人に考察されてきた桶狭間合戦は諸説入り乱れていて 今川義元の本陣についてもいくつも候補地があります
一説では公園から100mほど東にある「おけはざま山」が本陣とされていて…

民家の門前に石碑が建てられていました


ここを追われた義元がさきほどの桶狭間古戦場公園の方に逃れて…

この公園のある場所で戦死したのだということで 石碑が建てられたりもしています

義元公の馬を繋いだと伝わる"ねずの木"


こちらは首洗いの泉


公園には 信長と義元の銅像がたてられていました

ぐるっと見て回った後 再び「桶狭間古戦場伝説地」に戻ってきました

先ほどのパネルも撤去されていました

駅のホーム下のわかりにくい所に「よろいかけの松の石碑」が残されています

戦のあと 信長はここにあった松に鎧を掛け 兵たちが集まるのを待ったと伝えられています
大正時代まで松が残っていたそうですが 今はもうありません…
万歩計によれば ここまでの行程は63035歩
歩行距離は41.6kmだそうです👀

さすがに体力の限界を感じ 翌朝は全身筋肉痛でした(笑)
炎天下にアスファルトという悪条件も関係あるんでしょうね...^^;
古戦場伝説地にて記念撮影📸
「えい! えい! おー!」

長い記事をお読み下さりありがとうございました
てくてくシリーズはこれにて一旦終了(^_-)-☆
次回は 国東半島にある両子寺を訪れたお話です